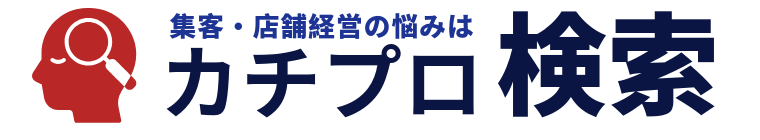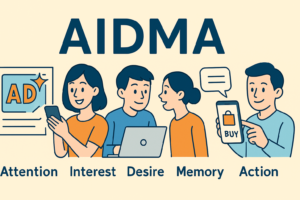フレーミング効果とは?ビジネスに役立つマーケティング理論

ビジネスで新規顧客を獲得するとき、商品やサービスをどのように伝えていますか?同じ商品やサービスでも、表現の仕方を変えるだけで顧客の反応は大きく変わります。これがフレーミング効果です。
本記事では、フレーミング効果の基本概念から、マーケティングでの具体的な活用法まで、経営者の方にわかりやすく解説します。お客様の心理を理解し、効果的な集客につなげるためのヒントがここにあります。
フレーミング効果をわかりやすく解説
フレーミング効果とは、同じ内容でも表現方法(フレーム)を変えることで、人々の判断や意思決定が変化する心理現象です。例えば「手術の成功率は95%です」と「手術の失敗率は5%です」は同じ確率を示していますが、前者の方が安心感を与えます。
私たちは論理的に判断しているつもりでも、実は表現方法に大きく影響されているのです。この効果を理解すれば、顧客コミュニケーションを効果的に設計できます。
フレーミング効果の基本概念
フレーミング効果の本質は「ものの見せ方」で印象を変える心理作用です。本質が同じでも、違う表現方法によって受ける印象が変わります。例えば「製品の満足度90%」と「製品に不満を持つのはわずか10%」は同じ情報ですが、前者の方が好印象です。
これは伝えたい情報を強調する見せ方をすることで、相手の受け止め方が変わり、意思決定に影響を与えるためです。私たちは常に情報を何らかの「枠組み」(フレーム)を通して受け取っており、そのフレームによって判断が左右されるのです。
アジア病問題の実験例
フレーミング効果を端的に表す有名な実験が「アジア病問題」です。この実験では、ある学生グループに「200人が助かる対策」と「3分の1の確率で600人全員が助かる対策」の選択を提示したところ、72%が前者を選びました。しかし別のグループには「400人が死ぬ対策」と「3分の1の確率で誰も死なない対策」という表現で提示したところ、今度は後者が78%を占めました。実は両方の選択肢は数学的には同じ内容なのです。
この結果は人間の心理に「損失回避性」があり、ポジティブな表現(救われる生命)とネガティブな表現(失われる生命)で意思決定が大きく変わることを示しています。
フレーミング効果は誰が提唱したのか?
フレーミング効果は1981年に、プリンストン大学のダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって共同研究の成果として発表されました。この研究は人間の意思決定プロセスに関する画期的な発見として認められ、後にカーネマンはノーベル経済学賞を受賞しています。彼らの研究は「人は常に合理的に判断する」という従来の経済学の前提に疑問を投げかけ、人間の判断の不合理性や認知バイアスの存在を科学的に証明しました。この発見はマーケティングだけでなく、政治や医療など様々な分野で応用されています。
行動経済学における位置づけ
フレーミング効果は行動経済学の中心的な概念の一つとして位置づけられています。行動経済学は従来の経済学が前提としていた「合理的経済人(ホモ・エコノミクス)」の考え方に疑問を投げかけ、人間の実際の意思決定は様々な心理的要因や認知バイアスの影響を受けることを研究する学問です。
フレーミング効果は、人間が必ずしも客観的な情報だけで判断するのではなく、その情報の提示方法や文脈に大きく影響されることを示す重要な発見でした。この概念はリチャード・セイラーやダン・アリエリーなどの研究者によってさらに発展し、マーケティングや公共政策など様々な分野で応用されています。現在では企業のマーケティング戦略や商品開発において、人間心理の理解に基づいたアプローチが不可欠となっています。
フレーミング効果はマーケティングではどのように使われているのか?
フレーミング効果はマーケティングの様々な場面で活用されています。商品の特徴をどう表現するか、価格をどう提示するか、リスクをどう伝えるかなど、顧客の意思決定に大きな影響を与えます。たとえば「90%脂肪カット」と「10%の脂肪を含む」では、同じ内容でも前者の方が健康的な印象を与えます。また、「1日たった100円」と「月額3,000円」も同じ料金でも印象が異なります。このように、フレーミング効果を理解することで、顧客の心理に沿った効果的なメッセージングが可能になり、売上向上や顧客獲得につながります。
利点を強調するフレーミング
商品やサービスの利点を強調するフレーミングは、特に食品や化粧品など、暮らしや健康を向上させる製品の販売に効果的です。例えば、新しいエステサロンの会員満足度を伝える場合、「満足いただいている会員が90%!」と「満足していない会員は10%だけ!」では同じ情報でも、前者の方が魅力的に感じられます。これは人間がポジティブな情報に対して好意的な印象を持ちやすいという心理に基づいています。
特に初めて購入する顧客に対しては、商品やサービスのメリットや成功例を強調することで、安心感を与え購入の後押しとなります。この手法は商品説明やキャッチコピー、広告文などで広く活用されており、顧客の関心を引き付けるために効果的です。
リスクを強調するフレーミング
サプリメントや防犯グッズなどの「予防商品」では、リスクを強調するフレーミングが効果的です。例えば「空き巣被害急増中!このサービスで防犯対策をすれば、もう空き巣の心配はありません」よりも「空き巣被害急増中!このサービスで防犯対策をしないと、次に狙われるのはあなたの家かもしれません」の方が強い印象を与えます。これは人間が獲得できる利益よりも失う可能性のある損失に対して敏感に反応する「損失回避性」を利用しています。
特に健康、安全、資産などに関わる商品・サービスでは、何もしないことのリスクを具体的に示すことで、顧客の危機感を喚起し行動を促すことができます。ただし過度な恐怖訴求は逆効果になる場合もあるため、適切なバランスが重要です。
数値表現を工夫するフレーミング
商品やサービスに関する数値情報の表現方法を工夫することも、フレーミング効果の活用法の一つです。例えば、「ビタミンC 5000mg配合」と「ビタミンC 5g配合」は同じ量ですが、単位を変えて数字を大きくすることで「たくさん入っている」という印象を与えることができます。逆に待ち時間などを伝える場合は、「1時間20分」よりも「80分」と表現すると短く感じられることもあります。
また割引率の表示でも「30%OFF」と「7割の価格でご提供」では印象が変わります。さらに調査結果などを示す際も、成功率と失敗率のどちらを強調するかで受け手の印象が大きく変わります。このように数値をどう表現するかによって、同じ情報でも顧客の受け取り方が変わることを理解し活用することが重要です。
極端性の回避による顧客単価アップ
人は選択肢が複数ある場合、極端なものを避け中間的な選択肢を選ぶ傾向があります。これを「極端回避性」と呼び、顧客単価アップに応用できます。例えば、化粧水2,980円、化粧水+シートパック3,500円、化粧水+シートパック+サプリメント6,800円という3つの選択肢を提示すると、多くの顧客は中間の3,500円を選びます。実際にテレマーケティングの現場では、最初に安い商品(梅)を注文したお客様に対して、中間(竹)と高価格(松)の選択肢も紹介すると、約7割のお客様が中間のプランにアップグレードするという結果も報告されています。
この手法は特に、すでに購入の意思を示している顧客に対して効果的であり、バックエンドセールスや契約更新時などに活用することで、自然な形で顧客単価を向上させることができます。
松竹梅の法則とフレーミング効果
松竹梅の法則は、商品を3つの価格帯(高・中・低)で提示すると、多くの人が中間の価格帯を選ぶという現象です。これは2025年4月時点でも多くのビジネスで活用されている効果的な手法です。例えば焼肉店で松8,000円、竹6,000円、梅4,000円のコースを用意すると、中間の「竹」が最も選ばれる傾向があります。この法則が働く理由は、人が極端な選択を避ける心理(極端回避性)にあります。最も高い選択肢は「贅沢すぎる」または「費用対効果が低いかも」と感じ、最も安い選択肢は「品質が低いかも」と懸念します。
西洋では「ゴルディロックス効果」と呼ばれるこの法則は、フレーミング効果と組み合わせることで、より効果的に使うことができます。例えば中間の選択肢の説明をより魅力的に表現したり、最も高い選択肢を最初に提示してアンカリング効果を利用したりすることで、顧客を自然に中間の選択肢へと誘導できます。
まとめ
フレーミング効果は、同じ情報でも表現方法を変えるだけで人々の判断や意思決定に大きな影響を与える心理現象です。カーネマンとトベルスキーによって提唱されたこの概念は、現代のマーケティングにおいて非常に重要な役割を果たしています。
マーケティングの現場では、利点を強調するフレーミング、リスクを強調するフレーミング、数値表現を工夫するフレーミングなど、様々な方法で活用されています。また、極端回避性を利用した顧客単価アップや松竹梅の法則との組み合わせにより、顧客の購買行動を効果的に誘導することが可能です。
フレーミング効果を理解し、適切に活用することで、新規顧客獲得やリピート率向上、顧客単価アップなど、ビジネスの様々な側面で成果を上げることができます。ただし、過度な誘導や誤解を招く表現は顧客の信頼を損なう可能性もあるため、誠実さと効果のバランスを常に意識することが重要です。
今後のマーケティング活動に、フレーミング効果という強力なツールを取り入れてみてはいかがでしょうか。適切な「枠組み」で情報を提示することで、お客様の心に響くコミュニケーションが実現し、ビジネスの成長につながるでしょう。
| フレーミング手法 | 使用場面 | 具体例 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 利点強調型 | 食品・化粧品など日常品 | 「満足度90%」vs「不満10%」 | 安心感と期待感を醸成 |
| リスク強調型 | 保険・セキュリティ製品 | 「対策しないと損失」vs「対策で安心」 | 危機感を喚起し行動を促進 |
| 数値表現型 | 成分表示・割引表示など | 「5000mg」vs「5g」 | 数値の印象を操作し価値感を高める |
| 極端回避型 | アップセル・クロスセル | 低・中・高の3プラン提示 | 中間価格帯の選択率向上 |
| 松竹梅型 | メニュー・プラン設計 | 高額・適正・低価格の3構成 | 販売したい商品の選択率向上 |