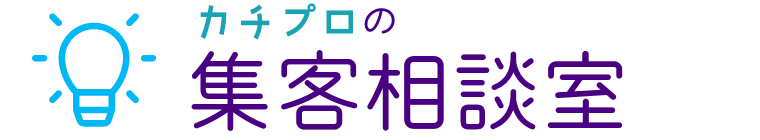ネーミングで大きく売れる!覚えやすい商品名をつけるコツとは?

適当に商品名を決めてしまう経営者も多いのですが、実は、同じ商品でもネーミングを変えただけで、売上や評価が異なります。ネーミングを工夫することで、その商品の価値を高め、死に筋だった商品も売れ筋にすることができます。そこで、今回はマーケティングにも活用できるネーミングのポイントを紹介します。
ネーミングとは?
マーケティングにおけるネーミングは、商品やサービスに記憶に残りやすい名前を付けることで、顧客の関心を引き、ブランドの認知度や売上の向上を目指す行為です。特徴的な名前をあえてつけることで、商品イメージを形成するのに役立ちます。
例えば、ポッキーは、棒状チョコ付きクッキーなど名前であれば確実に売れません。当初は、チョコスティックとテクテク歩きながら食べるイメージからネーミングをつけており、チョコテックという名前で販売されていたそうです。その後のテストセールの結果、ポキンの食べた時の響きから、ポッキーチョコレートと改名したそうです。
売れる商品を作る!ネーミングのヒントとは?
①ターゲットを意識する。
ネーミングをつける上で、対象顧客は誰であるのかを明確にしましょう。特に、対象顧客が絞られるような商品では尚更です。その商品に興味を持つのは顧客側であり、好奇心を持って触れてもらうことが第一の目標だからです。
よくネーミングは簡単で短い言葉が良いとされていますが、これはターゲットを誰にするかで異なります。長い方が商品の特徴を詰め込むことができるので、内容を重視する人には売れるからです。
②音からヒントを得る。
音からヒントを得てネーミングされた商品は、世の中にはとても多く存在します。
ポッキーもそうですが、カラカラという音がすることからネーミングされたソイカラや食べた時にガリガリと音がすることからネーミングされたガリガリ君があります。
③キーワードを組み合わせる。
短いキーワードを合わせることでネーミングすることもあります。
い・ろ・は・すのネーミングは、いろは歌に健康や環境を志向するキーワードであるロハスを掛け合わせてネーミングされています。これによって、柔らかなひらがなで国産の天然水であることを表現し、環境への配慮が具体的な行動となるきっかけを提案していく製品になるように思いが込められています。
この場合、基本的に読み方が難解にならず、発音しやすいネーミングであることがポイントになります。
④創意工夫した点を強調する。
例えば、チーズインハンバーグでも肉汁がしたたるようにしたり、チーズのトロトロ感にこだわりがあるのに、このネーミングでは顧客には伝わりません。
そのため、「肉汁したたるシェフのこだわりチーズハンバーグ」や「トロトロチーズが入った牛100%ハンバーグ」のようにPRすべきポイントをダイレクトにメニュー名に入れることでこだわりのポイントを伝えることが可能です。
⑤ダイレクトになんのために作ったのかを伝える。
例えば、接待を考えていたり、誕生日のお祝いを考えている場合、なんの説明もないコースが並んでいる場合、どれが最適なのかよくわかりません。そこで、「接待に最適!〇〇特製ごちそうコース」や「お誕生日のお祝い向け!シェフのセレクトコース」などのコース名をつけることで、すんなりコースを選択できるようになります。
⑥ネーミングは読めるのが前提である。
お〜いお茶は、当初は缶入り煎茶として販売されていましたが、ヒット商品とは言えない実績だったそうです。
そこで、伊藤園は1970年代に、新国劇の島田正吾さんを起用した“お~いお茶” と呼びかけるCMが好評だったことから、1985年に発売した緑茶飲料「缶入り煎茶」の名前を、1989年に「お~いお茶」へと変更したそうです。売れなかった原因は、煎茶の漢字が読めなかったことや煎茶が馴染みがなかったことだとされています。
例えば、フランス料理やイタリア料理では店名がそれぞれの国の言葉で書いており、読めないことがあります。読めないということは検索することができず、話題にするのも難しいということになります。Webがなかった当時ですらネーミングで売上が全く違っていることから、読み方がわからないことが売れない原因になっていてもおかしくはありません。
事例:単価が安い商品がネーミングを変更しただけで高値で取引
花卉の市場では、品種ごとに取引がされるため、一つの品種が揃った箱が高値で取引される傾向にあります。箱を作ると、本数がそれぞれあまり、余った花を箱詰めしてミックスとして取引されることがあります。このミックスは、顧客側からすると欲しい品種の本数が揃っていないため、価値は低く、価格も低くなりがちです。
そこで、花屋が直接セリを行う市場と取引を行うことをきっかけに、ミックスの箱の需要を上げるための工夫をしました。
ターゲット
加盟料を自己負担している花屋(鮮度を重視している)
商品
- ミックスの箱に入っている花は品質的に悪くはない。
- 他所ではやっていない水準の選別を行っていた。
これらの情報を伝えるためには、当然トレーサビリティーなどで情報開示できるようにすることも重要ではありますが、それも強い興味付けがなければ見られることはありません。そこで、ミックスと書いてしまいがちなパッケージにプレミアム感を出すためのネーミングをつけることにしました。
- 特殊な市場に参加している花屋さんなので、当然花にも詳しい。
- 生活の品質向上系の職業なので、ポジティブな言葉に感受性を持っていると推測。
- 当然、センスも求められる。
これらの情報から、「出荷された花は、消費者に対するメッセージだ。中身はお楽しみ」というコンセプトをつけて、花言葉も使い、「ミックス=感謝の花手紙」というネーミングを実施しました。そして、そのミックスの箱は、他の生産者のミックスとは違い独自のものであるブランド付けが行われ、高値で取引されるようになりました。
まとめ
たかが商品名だと思ってしまいがちですが、自分の子供に意味のない名前をつけないのと同じように、そのネームは体を表します。つまり、商品名はその商品価値を伝える重要なポイントでもあるわけです。
ネーミングが重要だとわかっていても慣れていないと良いネームは思いつくものではありませんので、ポイントを整理して即座にネーミングできるような訓練は必要です。
最終更新日 : 2023年12月13日