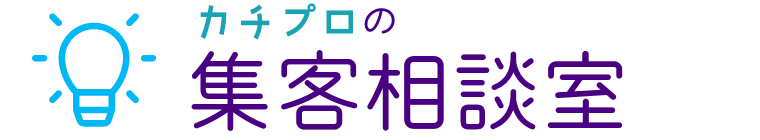デカ盛りメニューを飲食店が提供するのをおすすめしないわけとは?

デカ盛りメニューとは、画像や動画でわかるくらい量が多く、食器からはみ出ている料理のことを言います。デカ盛りメニューは、口コミが広まりやすく、集客に有利になる反面、原価が高くなることで利益を圧迫します。
また、それだけではなく、デカ盛りで話題になっている飲食店は、家族経営であり、家賃のかからない持ち家だったり、さらには内装や食材ももらっていることがあります。
そのため、例外の条件で飲食店を経営していることで、テナントで内装費をかけて経営している飲食店とは利益構造が大きく異なるため、デカ盛りの量で競争ができるわけです。
デカ盛りで利益が出る飲食店がある理由
激安デカ盛りの提供は、テレビ番組などで取り上げられることが多く、視聴率が高くなることが一般的です。しかし、ほぼ全てが赤字となる一品であり、飲食店にとっては経営が健全ではないとの指摘もあります。
デカ盛りが提供できる飲食店では、以下のような条件を揃えているのであり、通常の仕入れやテナントを借りていると、デカ盛りを提供することは不可能です。
家族経営で人件費がかからないから
原価と人件費は、飲食店の経営の中の費用では大きな割合を占めており、合わせてFLコストと呼ばれています。FLコストは、売上に対して60%以内が基準です。人件費がかからないように家族経営にしたり、全席カウンターにして1人で経営ができるようにすることで、費用を大きく削減することができます。その分を食材費にかけることができるので、単純に量を増やしている場合があります。
料理に使っている素材を自分で供給し、原価がかからないから
自分の畑で使っている素材を供給している飲食店は、仕入れに支払う毎月の支払いが節約されます。そのため、その分だけ、1人に提供できる原材料を増やすことができ、結果的にデカ盛りにできている店舗も存在します。また、デカ盛りを提供しているお店には、その地域の住民と家族のような関係性を持っているお店も多いので、食材を顧客が無料で持ってきてくれることもあります。
持ち家および修繕費をかけない経営を行っているから
デカ盛りのお店は、古いお店が多く、内装もボロボロだったり、使っているテーブルも揃っていないことがあります。これは、持ち家を改造し、その上で内装にお金をかけないことで、毎月の売上の10%相当になる家賃をかけない経営をしています。その分、食材費に還元することで、量を増やし、デカ盛りにしています。
デカ盛りが飲食店の集客に与える影響とは?

デカ盛りにすることで、口コミされやすくなるため、集客に良い影響を及ぼします。また、番組やインフルエンサーの企画にも合致しやすく、メディアに取り上げえられやすくなります。それを見た一般ユーザーが、デカ盛りを体験するために来店し、InstagramなどのSNSに投稿することで、さらに顧客が集まります。
デカ盛りにすることの飲食店側のデメリットとは?
デカ盛りで提供する飲食店のデメリットはとても多いです。
デカ盛りは、食材費が上がるだけではなく、調理時間を長くします。そのため、メニューを提供する生産性が悪くなり、回転率を下げる点で悪影響があります。
また、安い食材は、円安の影響などで高くなっており、量を重視するためには、食材を質を下げる必要があります。食材の質は、味に影響しますので、口コミが悪くなり、集客に悪い影響が出始めます。
さらに、強烈なデカ盛りの印象は、一度口コミが広まると、そのイメージで固定化されてしまいます。そのため、その他の戦略が選択しづらくなり結果として、集客以外の要因で経営が続かなくなりがちです。
デカ盛りを採用する場合は基準を設ける
デカ盛りはメリットよりもリスクの方が多いので、全てのメニューをデカ盛りで提供するのは、まず自殺行為です。ただし、昨今は、食材費高騰の影響で、どの飲食店も量が減っているので、相対的に多い量で提供することで強い引きになることは間違いありません。
この時、何でも量を増やすのではなく、安く仕入れることができる食材の量を増やしたり、安価に仕入れることができた食材を使って日替わりメニューを作る工夫をするのが良いでしょう。
最終更新日 : 2024年7月17日