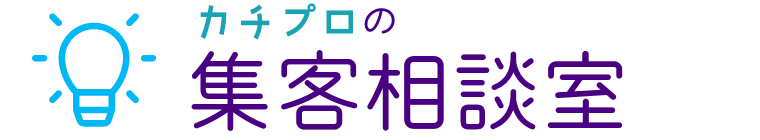マーケティングミックスとは?4Pと4Cの活用事例とは?

マーケティングミックスとは、マーケティングの実行戦略です。市場や自社の分析に基づき具体的な施策を考えるステップです。製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)の4つの要素を組み合わせて施策を検討するため、「4P」とも呼ばれます。「ミックス」の名の通り、これらの要素を適切に混ぜ合わせることで最適なマーケティング戦略を作り出します。
また、これらの派生には、「Customer Value(顧客価値)」「Cost(コスト)」「Convenience(利便性)」「Communication(コミュニケーション)」の4Cと、「Commodity(共生商品)」「Cost(コスト)」「Channel(流通)」「Communication(コミュニケーション)」の共生の4Cがあります。
4Pとは?経営資源を視点にしたフレームワーク

マーケティングミックスといえば4P分析が代表的です。4P分析とは、「Product(商品・サービス開発)」「Price(価格決定)」「Place(流通)」「Promotion(集客・販売促進)」の4つの観点で構成される企業の経営資源や強みを中心においた視点でのマーケティング戦略の立案を行うフレームワークです。
マーケティングの父、フィリップ・コトラーのの理論では、マーケティング1.0に対応しています。マーケティング1.0はいかに製品を販売促進するのかが着眼点になっています。
Product(商品・サービス開発)
市場に投入する商品やサービスの開発を行います。4P分析の前に、市場を分析するSTP分析やペルソナの設定を行いますので、標的市場の顧客ニーズを要点を具体化し、ニーズを満たす魅力的な機能性を持った商品開発を実施します。
例えば、スターバックスやマクドナルドは世界展開している飲食業ですが、どの地域でも全く同じメニューを提供しているわけではありません。抹茶などは日本限定のメニューで提供されることが多く、ハンバーガーなどのサイズは、日本人の胃袋にあったサイズで提供されています。

Price(価格決定)
価格設定は売上に直接影響を与えます。価格決定で重要なのは、地域相場と需要の価格弾力性です。地域相場は、その地域の人にとって、その商品やサービスの価格の正当性を決める基準です。そして、需要の価格弾力性は、値上がりすることで需要が低くなる度合いのことを意味しています。需要の価格弾力性が高い商品やサービスは、値上げをすることで、需要が大きく下がるため、値上げが非常に難しい商品です。逆に、需要の価格弾力性が低い商品は、値上げをしても需要に変化がなく、値上げがしやすい商品です。
地域相場の例で言えば、都市部と地方の料理の相場の違いです。また、需要の価格弾力性が高い商品は、値下げをすることで需要が大きく高くなることを意味しています。そのため、来店数を増やす目的で、バナナのようなものは集客商品として使われます。
Place(流通)
流通とは、商品やサービスを消費者に届けるまでのプロセスを設計することです。例えば、メーカーが商品やサービスを直接消費者に提供する方法は、煩雑になっています。そのため、中間事業者として、卸売業者・代理店、小売店などを入れることで、もっと幅広い消費者に流通させることができます。
最近では、メーカーがSNSなどで商品やサービスのプレゼンテーションを行い、受注生産を基本にして商品を販売するD2C(DIRECT TO CUSTOMER)が普及しています。また、中間手数料を除外するために、自社ブランドを作り、ウェブで通信販売を行うケースも増えています。

Promotion(集客・販売促進)
プロモーションは、商品やサービスの情報を標的市場に伝えることで、それらの商品価値を認知してもらい、購入に結びつけます。プロモーションの戦略は、顧客の購買活動を基準に立案します。消費者行動のフレームワークでは、AIDMAやAISASが有名です。

4C分析とは?「顧客目線」のフレームワーク
ものが溢れ、顧客に選択肢が増えるにつれて、顧客目線の商品やサービスの開発が重要視されるようになりました。4C分析とは、「Customer Value(顧客価値)」「Cost(コスト)」「Convenience(利便性)」「Communication(コミュニケーション)」の4つの顧客視点のマーケティング戦略の立案を行うフレームワークです。
コトラーの理論では、マーケティング2.0に該当し、消費者志向に該当します。
4P分析の4つの要素と4C分析の4つの要素はそれぞれ対応しています。
- Product → Customer Value
- Price → Cost
- Place →Convenience
- Promotion → Communication
Customer Value(顧客価値)
顧客価値とは、顧客を求める価値のことです。顧客は、商品やサービスの性能、品質、デザイン、アフターサービスやブランド力などの複数の要素に価値を求めています。企業側は、標的市場の分析やペルソナを用いて顧客理解を行い、顧客価値を具体化します。
Cost(コスト)
コストとは、顧客が商品やサービスを入手する時に必要な費用のことです。
価格設定と決定的な違いは、コスト戦略では顧客価値が基準に設定される点です。例えば、顧客価値を超過した高性能の家電製品は、その分だけ高価格に設定しなければなりません。これは、「本来欲しかった価値を欲しくなかった価値分だけ高く購入している」ことで、顧客目線では「高い」と判定されます。たとえ、低価格でも顧客価値を満たしていない商品やサービスは「高い」とみなされます。
Convinience(利便性)
利便性とは、顧客がその商品やサービスを手に入れる難易度を表しています。利便性が良いことは、商品やサービスを購入するまでの手間がかからない状態を指し、スムーズに購入することができます。
Communication(コミュニケーション)
コミュニケーションとは、顧客との接点を作り、関係性の維持、新しい商品やサービスの情報発信、顧客側からの情報収集などを行うことです。
SNS、DMの送付、イベントの開催を行うことで、商品やサービスの認知度の拡大やブランドとの関係性の向上を行うことで、購買に良い影響を与えることを目的にしています。また、コミュニケーションを積極的に行うことで、顧客からのアンケートをとることができ、より深く顧客理解をすることができ、顧客価値のブラッシュアップや新しい商品開発に役立てることができます。
共生の4Cとは?
環境問題が深刻化し、経営戦略に環境への考慮が必要とされる時代が到来しました。環境への配慮がなければ、支持されるブランドにはならないということで、経営資源に環境が含まれて、経営の六資源(ヒト、モノ、カネ、情報、時間、環境)で考える必要性が謳われています。
共生が必要とされるマーケティング3.0に対応したフレームワークです。
共生の4Cでは、「Commodity(共生商品)」「Cost(コスト)」「Channel(流通)」「Communication(コミュニケーション)」の要素に分かれています。
クラウドファウンディングの仕組みや福祉ビジネスが、マーケティング3.0の仕組みにちょうど該当します。
Commodity(共生商品)
プロダクトアウト(生産主義)では、売り手が作った商品には在庫が発生し、それらを売り切るために、生産地や機能を偽装する行為が減りません。そこで、消費者からの意見を吸い上げた商品やサービスを開発することで、共に幸せになるWin-Winの関係性になるような関係性を構築することを目指します。
Cost(コスト)
この場合のコストは消費者が商品を入手するためにかかるコストではなく、共生するために必要な費用全体を指します。販売コスト、生産コスト、移動や手数料などの入手コスト、社会的コストの全てに拡大解釈が可能です。
例えば、福祉の問題がこれに該当します。企業が社内託児所を作ることで、従業員の福祉が守られます。これによって、有料企業と福祉ビジネスとの社会的コストでwin-winの関係性が成立し、共生が成立します。
Channel(流通)
納入業者、製造業者、流通業者、消費者が共生している流通経路を作ることが挙げられます。
例えば、CtoCビジネスモデル(消費者間取引)のフリーマーケットアプリでは、個人間の取引はプラットフォームが行い、流通は、コンビニで受け渡し、特定の流通事業者が相手方に運送するという仕組みが成立します。
Communication(コミュニケーション)
SNSが一般的になってきたことで、双方のコミュニケーションが簡単になりました。価値共創型で消費者の心を掴み、広告などで社会問題の解決を提案することが、その企業の明確な立ち位置を構築することにもつながります。
コミュニケーションをこれらの手段として活用し、口コミやセミナーなどで認知度が拡大していきます。
マーケティングミックス(4P)をスターバックスの事例で解説
マーケティングミックスは、大手企業であれば、基本的なフレームワークとして活用されます。その中でも、やはり注目されるのは、シンプルなマーケティングを展開しているスターバックスでしょう。
1971年にアメリカ・シアトルで創業されたスターバックスは、現在では世界中で知られるカフェチェーンに成長しました。
| Product(製品) | スターバックスの提供する商品は国によって異なり、日本では抹茶系ドリンクやショートサイズなど、日本独自の商品展開が行われています。 |
| Price(価格) | スターバックスのコーヒーは、他のカフェチェーンやコンビニのコーヒーよりは割高ですが、ホテルのラウンジや喫茶店よりは安い価格設定がされています。Third Placeのコンセプトとして気軽に利用しやすい空間に滞在することができます。 |
| Place(流通) | スターバックスは、ターゲット層にインパクトを与えるために、銀座に一号店を出店しました。また、好立地に店舗を自社展開をしており、繁華街では集中出店戦略(ドミナント出店)を採用し、利便性を高めています。 |
| Promotion(プロモーション) | スターバックスは広告宣伝活動を一切行わず、ユーザーからの口コミとPRのみでプロモーションを行っています。たとえば、毎月のように入れ替わるフラペチーノは、ロゴ入りのグラスでユーザーが投稿するため、豊富なユーザー生成コンテンツ(UGC)で溢れていて、体験意欲を掻き立てています。 |
スターバックスは、ターゲット層の選定、商品の品質、店のコンセプトなど、マーケティングミックス(4P)を的確に活用することで、日本国内での成功を収めています。その結果、2023年3月末までの段階で、 日本には 1,811店のスターバックスが存在します。
マーケティングミックスは、マーケティング戦略から実行のプロセスのどの位置に属すのか?
マーケティングミックスは、マーケティング戦略立案の中では、マーケティングリサーチ、STP分析の次に実行するものであり、下流の位置に該当しています。
マーケティング戦略の立案に使う情報を収集します。統計のほか、対象市場に出向くことや、競合がどのようなマーケティングを行っているのか、ライフスタイルを分析し、有効なコミュニケーション方法を割り出すことも重要になります。
外部環境を理解し、明確な標的市場を設定するために、STP分析を実行します。STP分析の方法については、「STP分析とは?マーケティング戦略の立案に必要な外部要因の分析方法」にて解説しています。
企業視点の4P分析と顧客視点の4C分析は、経営資源からやるべきマーケティングを明確化する視点と、顧客ニーズから要点整理をするのに役立つため、どちらも実施することが一般的です。
PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回していきます。実行しただけでは、うまくいっているのかがわかりませんので、必ず、実施する前に目的にあった指標を設定し、成功の目標値を設定します。それに基づいて評価を設定し、目標達成ができていなければ、マーケティングの改善を行います。
まとめ
マーケティングミックスは、他社の戦略をわかりやすく説明したり、自社との違いを説明する際によく使うフレームワークでもあります。
なんどもいうように、用語自体にはなんの意味もありません。重要なのは、購入というものが商圏内で起こる相対評価の結果であることを理解し、ライバルを知り、評価される明らかなマーケティング上の強みを構築することです。
マーケティングの独学方法を紹介しています。ちょっと破天荒な発想ではありますが、実践をやりつつ学ぶのが一番知識として入ってくるやり方です。
最終更新日 : 2024年4月20日