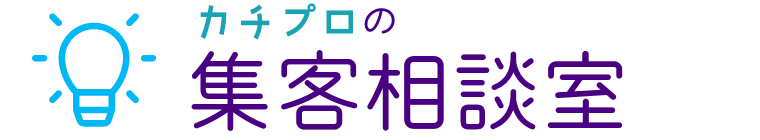リピーターの作り方とは?ビジネスの基本でもあるリピーターの増やし方

新規顧客の集客は、市場規模が有限であることから無限にできるものではありません。特に規模が小さく人口流入が少ない地方での地域密着型のビジネスでは、新規顧客の獲得の難易度が都市部に比べると高いため、顧客の定着を図らなければなりません。そのため、リピーターを効率良く作っていくための施策が重要になります。
集客のサクセスパートナーでは、集客のコンサルティング・ディレクション業務を行っています。
客数・売上増加を効率的にしたい事業者は、お気軽にご相談ください。
なぜ、リピーターが重要なのか?

新規顧客をリピーターにすることの重要性は、競争力、利益率、売上高を上げるためにはリピート率の向上が必須だからです。
リピーターと競争力の関係性
例えば、特定の市場の規模が1万人で、新規顧客の獲得が初年度に1,000人であった時は、残りの新規顧客として取り込めるのは、9,000人です。リピーターとして顧客定着しないビジネスでは、商品やサービスが期待値を下回るため顧客が流出することで、口コミによる新規顧客の獲得が困難になるため、競争力に強く影響します。
リピーターと利益率の関係性
リピーターが利益率に関わっているのは様々な法則で言われています。例えば、5:25の法則では、5%の顧客離れを防ぐことができれば25%の利益率が改善されるという法則です。また、新規顧客の集客は、リピーターの集客の5倍かかるといった1:5の法則があります。つまり、リピーターを効率良く増やすことは、利益率を高めることになります。
リピーターと売上の関係性
全体の売上の7~8割は、上位顧客2~3割の売上が占めています。この法則をパレートの法則(20:80の法則)と呼びます。この法則から、リピーターを増やすことで、上位顧客2~3割からの売上金額が増えるため、大きな売上アップになります。
リピーターを作るための方法とは?

体験価値を高める対策を行う。
体験価値とは、簡単に言ってしまえばサービスを受けた際の主観です。主観なので、人によって体験価値は異なります。そのため、どんなにサービスをブラッシュアップしたとしても、満点にすることはできません。(高級品を扱っている場合は、価格による客層のフィルターがかかるため、体験価値の向上の精度を上げることができます。)
体験価値を高めるためには、事前に抱いた期待を上回る体験を提供します。逆に、事前に抱いた期待を大きく下回る出来事があれば、体験価値はどんなに価値の高いものを提供していようが下がります。また、顧客ごとに価値を感じるポイントが完全に違っていますので、顧客管理を行い、顧客1人1人に合わせたサービスを提供します。
例えば、高級レストランで、美味しい料理を食べていた時に、そそくさとしたウェイターの対応を見て、幻滅したとします。この場合、実際の価値がプラスでも、幻滅した出来事で、そのレストランへの体験価値は下がります。体験価値は、例えばコースに含まれない旬なメニューの差し入れやちょっとした気の利いたトークで上げることもできます。
再購入のきっかけを作る
再購入をきっかけを作ることで、リピーターになりやすくなります。これには、定期的なプロモーションや割引、新商品の案内などがあります。また、ロイヤルティプログラムを設けることで、リピート購入を促すことができます。
コミュニケーションを強化する
顧客とのコミュニケーションを密にすることで、顧客のニーズや要望を把握し、それに応える形でサービスを提供します。メールマーケティングやSNSを活用して、定期的に情報を発信することも有効です。この時のコミュニケーション方法は、顧客の大半が利用しているものを選ぶのが良いでしょう。ビジネス向けのサービスであれば、メールを使っている顧客がほとんどですし、一般消費者向けのサービスであれば、LINEを使ってメッセージのやり取りを行っています。
名物に力を入れる。
名物や人気サービスをブラッシュアップすることは、体験価値を上げることにも役立ちます。何故ならば、新規顧客は、何を選ぶことが正解なのかわかりません。食堂で条件反射で日替わり定食を選んでしまうように、情報がないから選べないのです。
選ばれやすい名物に力を入れれば、特別な演出がなくても体験価値を高めることができます。
リピーターを増やす具体的な手法

リピーターを作り、維持する具体的な方法について解説します。
サブスクリプション(通称サブスク)
サブスクリプション(通称サブスク)は、定期的な支払いを行うことでサービスや商品を受けられるビジネスモデルです。日本では主に月額制が一般的です。このモデルを採用することで、顧客が月に1回以上確実に利用する環境を作ることができます。
サブスクの導入は、顧客の利用頻度を一定に保つ大きなメリットがあります。しかし、デメリットも存在します。例えば、サービスが単調であれば顧客が飽きて解約する可能性があります。また、サービス提供に問題が発生すると、顧客の信頼を失いやすいです。
サブスクを成功させるためには、必要性の高いサービスや負担の少ないサービスに焦点を当てることが重要です。例えば、食べ放題のサブスクがメディアで話題になり、需要が急増した場合でも、サービス提供が安定していないと方針転換が必要になるケースもあります。
サブスクモデルは、顧客との継続的な関係を築くために有効な手段ですが、その運用には慎重な計画と継続的な改善が必要です。
ポイント制度・ランクアップカード
大手カフェチェーンのドトールやスターバックスのように、店舗で使えるポイント制度を導入することで、リピーターを作る効果があります。この仕組みは、事前に一括で支払いを済ませることで、後の利用が促される形になっています。
顧客は前払いした金額分のサービスを最大限に活用しようと考えるため、リピート率が高まります。このような前払い制度は、回数券と同じ原理に基づいています。
ポイントが一定数貯まると、より良いサービスを受けられるランクアップカードを提供する店舗も多いです。これにより、顧客はさらに店舗を利用する意欲が高まります。ITを活用することで、このようなポイント制度やランクアップカードの仕組みは比較的容易に構築できます。データ管理も効率化され、顧客の購買履歴や嗜好を把握しやすくなります。
ポイント制度とランクアップカードは、顧客のリピートを促す有効な手段です。ITを活用してこれらの仕組みを導入することで、リピーターの確保と顧客満足度の向上が期待できます。
LINE公式アカウント
LINE公式アカウントは、顧客と直接コミュニケーションを取ることができるツールです。
使い方としては、新商品の案内や特別なプロモーション、イベント情報などを定期的に発信することで、顧客の興味を持続させます。これにより、顧客が再度利用するきっかけを作ることができます。また、LINE公式アカウントから配信する限定クーポンや特典を提供することで、顧客に次回利用するインセンティブを与えます。これがリピート率の向上に寄与します。
顧客からの問い合わせやフィードバックに迅速かつ丁寧に対応することで、顧客満足度を高めます。高い満足度は、リピーターを作る上で非常に重要です。LINE公式アカウントはサードパーティー(別企業)が開発したネット予約・自動応答の機能と連携させることで、これを実現します。
LINE公式アカウントでは、顧客の行動データやメッセージの開封率などを分析することができます。このデータを活用して、顧客に合わせたパーソナライズされたコンテンツを提供することで、リピート率を高めることが可能です。
メールマガジン
メールマガジンは、顧客に直接情報を届けることができる手段の一つです。このツールをうまく活用することで、リピーターを作る多くの機会が生まれます。
使い方としては、新商品の紹介やセール情報、イベントの告知などを定期的に送ることで、顧客の関心を持続的に維持します。これが次回の購入や利用のきっかけとなり、リピート率が向上します。また、メールマガジン限定のクーポンや特別な割引を提供することで、顧客に再度利用する動機を与えます。特典があると感じれば、顧客はメールマガジンを開封し、リピート購入を行いやすくなります。
役立つ情報や業界のトレンド、使い方のコツなど、顧客が価値を感じるコンテンツを提供することで、顧客満足度を高めます。満足度が高いと、リピートする確率も高まります。
開封率やクリック率などのデータを分析し、顧客の興味や行動に基づいてコンテンツをパーソナライズします。これにより、顧客が関心を持つ情報を提供でき、リピート率を高めることができます。
DM(ダイレクトメール)
ダイレクトメール(DM)は、顧客個々に対して直接郵送する形で情報を提供する手法です。この方法を活用することで、リピーターを作るいくつかのアプローチがあります。
DMは個々の顧客に対してパーソナライズされた情報を提供できます。これにより、顧客は特別感を感じ、リピートする動機が生まれます。通信販売では、主に季節の変わり目にカタログを送付することが多いため、年に4回のペースで送付するケースが多いです。
購入後の感想を聞いたり、次回購入時の割引を提案するなど、フォローアップを行うことで、顧客満足度を高めます。高い満足度は、リピートする確率を高める要素です。
ニュースペーパー
ニュースペーパーは、主に店舗やイベントで配布される無料または有料の情報誌です。この古典的なメディアを活用することで、リピーターを作る効果があります。
新商品の紹介や店舗のイベント、スタッフのインタビューなどを掲載することで、ブランドイメージを強化します。顧客は定期的に新しい情報を得ることができ、リピートする動機が生まれます。また、ニュースペーパー内に特別なオファーを掲載することで、顧客に次回の利用を促します。このような特典があれば、顧客はニュースペーパーを手に取り、再度利用する可能性が高まります。
業界のトレンドや裏話、顧客の声など、単なる商品情報以上のコンテンツを提供することで、顧客満足度を高めます。これがリピーターを作る上で有効です。地域のイベントやコミュニティと連携してニュースペーパーを配布することで、新たな顧客層にリーチすることができます。新規顧客を獲得するとともに、既存の顧客もリピートしやすくなります。
スタンプカード
スタンプカードは、顧客が一定回数利用するごとにスタンプを押し、特定の回数が集まったら特典を提供するというシンプルながら効果的な手法です。
スタンプが一定数貯まると、無料商品や割引サービスなどの報酬を提供します。これが顧客にとって次回利用する大きな動機となり、リピート率が高まります。10回来店で無料サービスが一般的ですが、あまりにも長い道のりで期限がないとあまり効果を発揮しません。そのため、有効期限を1~2ヶ月と短く設定し、3回来店で無料サービスと小さな達成感にすることで、来店のペースメーカーになります。
スタンプカードは、導入が容易で運用コストも低いです。そのため、小規模な店舗でも気軽に始められ、リピーター作りに効果を発揮します。
リピーターを作る方法のまとめ
リピーターの確保は、企業の成長と継続的な成功にとって最重要の要素です。新規顧客の獲得よりも、既存の顧客をリピーターにする方がコストパフォーマンスが高いとされています。リピーターを作るためには、まず体験価値を高めることが必要です。商品やサービスの質はもちろん、顧客サービスやアフターケアも含めて、顧客に高い満足度を提供する必要があります。さらに、継続的なコミュニケーションも重要です。メールマガジンやDMなどを活用して、顧客に定期的に有益な情報や特典を提供しましょう。
また、リピーターを維持するためには、顧客管理でしっかりとデータを収集することが不可欠です。特に店舗運営においては、POSシステムの導入が必須となります。これにより、顧客の購買履歴や嗜好を把握し、パーソナライズされたサービスを提供することが可能になります。
POSシステムに関してよくわかるホワイトペーパーを株式会社スマレジが提供しています。一度どんなことができるのか見てみると良いでしょう。

5分でわかるPOSレジの教科書
POSは、キャッシュレス決済導入だけでなく、会計、顧客管理、予約管理、集客ツールと連携する店舗経営を管理する重要なシステムです。POSでできることを簡単に理解!
最終更新日 : 2023年10月31日