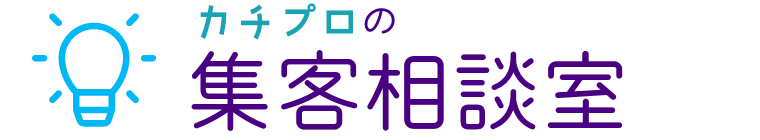飲食店の売上を向上させる方法とは?具体的な戦略を解説
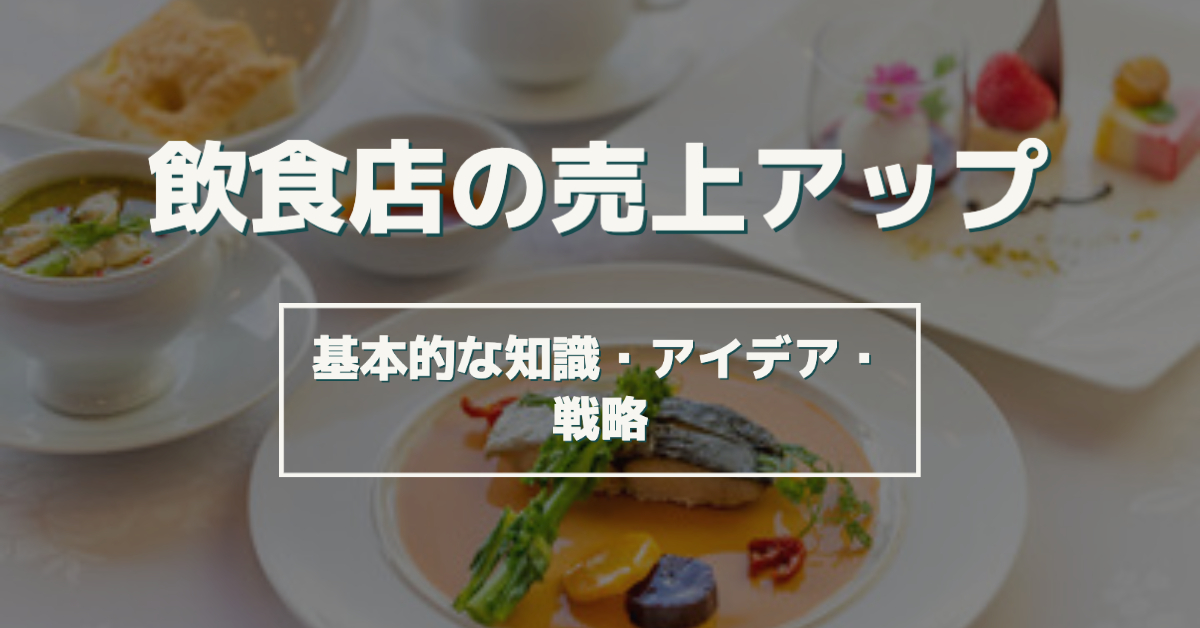
飲食店は、競争が激しいとされていますが、1人あたり1日3食ありますので、美容室や整体院などに比べると、消費の回数自体は多く、業態を工夫すれば、集客の機会はかなり多い方です。また、行動心理学と組み合わせることで単価を上げることもできます。
飲食店の売上を大きく向上させる具体的な方法には、テンプレートのようなものもあります。ここでは、可能な限り具体的な売上アップの手法を解説していきたいと思います。
飲食店の集客の成功事例を紹介
飲食店向けの集客コンサルティングサービスを提供しています。コンサルティングできっかけを掴み、集客のコントロールを掴んだ事例を紹介します。
都心の居酒屋の売上が2倍に

オンラインとオフラインの視認性を高めて、予約数が爆増!
地方のレストランのHPを改善

ホームページリニューアルを伝えた日に100件の予約が入り、その後も事業全体の成長に貢献。売上を25%伸ばすことに成功しました。
メディアの機会を予約に直結

番組の企画とリンクさせた企画とプロモーションで、新規の予約数を大量獲得
口コミ数を2倍に

口コミの依頼方法を工夫して、1年で口コミの獲得数を平均2倍に
ウェブサイトのアクセス数を5倍に

関連性の高いコンテンツを追加して、ウェブサイトの訪問者数を5倍に。地域系キーワードでGoogleで1位に
\ ウェブサイトが安い!代行ありのコンサルティングプラン登場 /
飲食店の売上を上げるためには?
飲食店の売上を向上させるためには、具体的に何を向上させるべきなのかを明確にすることが重要です。これには、売上の法定式を構成する要素を理解し、解釈していきます。
大枠を知るための売上の法定式
売上高=取引回数(回)×顧客単価=客数(人)×顧客単価×来店頻度
これらの要素を解説すると以下のようになります。
| 客数の増加 | 新規顧客の獲得。客数の総数を決める要素なので重要。ただし、難易度やコストも高く、客数の増加ばかりに注力すると、利益が上がらない。 |
|---|---|
| 顧客単価の向上 | ワンランク上のメニューを薦めるアップセルや、サイドメニューを薦めるクロスセルが基本。 複数のランク帯を用意することで、単価を調整する。 |
| 来店頻度の増加 | 新規顧客を固定客化する。新規顧客は何もしないと、8~9割客離れを起こす。そのため、この割合を低下させる対策を行うことで、コストをかけずに1人あたりの売上を伸ばす。コストが低く、利益が出やすくなる。 |
売上を上げるためには、単純にこれらの3つの要素を向上させます。もしくは、どれかを捨てて、その他の要素を大きく上げることで可能です。客数を伸ばしたい時に、値引きをしたりすることもありますが、過度な値引きは、客層そのものを入れ替えてしまうリスクがありますので、最初のターゲティングが重要と言えます。
詳細に具体化するための売上の方程式
1回の営業の売上を概算する方程式は、以下のように分解することができます。
売上 = 席数 × 回転数 × 客席稼働率 × 客単価
席数と客席稼働率は集客ですので、ここで考える必要があるのは回転数です。回転数はランチとディナーでも考え方が違います。ランチの場合は、提供までにかかる時間と滞在時間の短縮化が効果があります。また、ディナーの場合は、コース予約であれば、回転数を増やすということは、入店時間や2件目、3件目の可能性がありますので、時間帯によって提供するコースを変更するなど利用しやすくすることで、回転数を上げることもできます。
また、曜日や時間帯によって、顧客単価と集客の難易度も変わってきます。概算では以下のように考えますが、得意な曜日と苦手な曜日を振り分けて対策を考える必要性はあります。ただし、苦手な曜日を休業日にしてしまうのも対策です。
昼(平日): 30席 × 2回転 × 0.7稼働率 × 1,000円 × 16日=672,000
夜(平日): 30席 × 1回転 × 0.7稼働率 × 3,500円 × 16日=1,176,000
昼(週末): 30席 × 1.5回転 × 0.7稼働率 × 1,500円 × 8日=378,000
夜(週末): 30席 × 1.5回転 × 0.7稼働率 × 4,000円 × 12日=1,512,000
合計:3,738,000円
飲食店の売上を向上させる具体的な方法を解説
飲食店の売上を向上させるための具体的な方法について解説をしたいと思います。飲食店の集客方法については別の記事で解説していますので、今回は、より詳細な戦略を重視して説明します。
看板メニューのブランディングをする
飲食店の口コミは、店名だけで拡散されることはほぼありません。そのお店を代表する看板メニューがあります。例えば、A店の看板メニューがハンバーグであれば、「ハンバーグといえばA店」「A店といえばハンバーグ」というような口コミが拡散されます。これが、何でも美味しいと言い張ってしまうと、口コミは拡散しなくなります。
看板メニューとして認知してもらうためには、競合他店に比べても、看板メニューの品質が高いことはもちろんのこと、自分から看板メニューはこれだと言い切る必要があります。例えば、店内の券売機やメニュー表、接客などで看板メニューを積極的におすすめします。また、可能な限り多くの人に食べてもらう必要がありますので、ランチタイムで提供します。
この看板メニューを基軸に、トッピングやサイドメニューを拡充したり、手間のかからないハンバーグを使った派生メニューを用意するなどして、単価を向上させていきます。これにより、評判を向上させた上で、売上も向上させることが見込めます。
松竹梅・特上の価格設定にする
行動心理学には、最下位と最上位が回避され、中位が最も選択される、極端性の回避と呼ばれる現象があります。ここから中位のプランを顧客単価に設定することで、顧客単価を引き上げることができます。日本ではこれを松竹梅の法則と呼びます。コースメニューであれば、共通のメニューを肉付けすることで3つのコースを作ります。
梅:名物メニューA+名物メニューB+α
竹:名物メニューA+名物メニューB+名物メニューC+名物メニューD+α
松:名物メニューA’+名物メニューB’+名物メニューC’+名物メニューD’+α
この他にイレギュラーコースとして、接待用の特上コースを用意します。これにより、最上位プランが一個増えますので、平均顧客単価を上げることができます。
高単価戦略を基本にする
立地が悪いと単価を下げて客数を増やそうとしますが、目標売上に必要な客数を増やしてしまうため、意味がありません。また、低価格戦略は使える食材を限定してしまうため、なかなか評判になりづらく、広告費もかけることができません。そのため、立地が悪い店舗ほど、高単価戦略をベースにして、食材や広告を選べるようにしましょう。
限定メニューを戦略的に使う
スターバックスは、限定のフラペチーノやドリンクを毎月のように入れ替えて販売をしており、真冬でも強い集客力があります。フラペチーノのようなスイーツでもあり、ドリンクでもあり、価格としても1,000円に満たない看板の限定メニューは、スイーツの代替品にもなっているため、幅広い客層の顧客を集めることができます。また、スターバックスは、SNSでの発信に加え、口コミが広がることを意識しているため、広告費をかけずに集客をすることに成功しています。
マクドナルドも、月見バーガーやてりたまバーガー、グラコロバーガーなどをレギュラーメニューにしていません。人気のあるメニューでもあえてレギュラーにしないことで、集客が弱い月の集客力の担保を作っていると言えます。
ドミナント出店で良質な商圏を囲い込む
ドミナント出店は、特定の高品質な商圏に集中出店をすることで、ブランド認知度を高め、配送コストを削減するための戦略です。この戦略は、大手コンビニエンスストアチェーンのセブンイレブンが採用しています。
商圏を広げると労力と費用の面でマーケティングコストが高くかかります。そのため、商圏を絞り込んだ方が、新店舗の告知を既存店舗でできるなどの工夫を行うことができ、有利なマーケティングをすることができます。また店舗数を増やすことで、顧客接点(タッチポイント)を増やすことができます。
ただし、同じ形態の店舗を増やすと、顧客の入れ替わり(カニバリゼーション)が起こる可能性があります。そのため、異なる業態の店舗での差別化が必要です。
LINE公式アカウントをカスタマイズして運用する
売上を上げるためには、利便性を上げて予約を取りやすくしたり、こちらからメッセージを発信して来店動機を与えるようにすることが定石です。店舗アプリは、スマホの容量がかかり、ダウンロードも嫌がられるため、あまり広がりません。
LINE公式アカウントは、LINEで動作し、LINEでメッセージを配信ができます。また、リッチメニューで各サービスに直リンクを設置できるため、ぐるなびやUberEatsと連携させることで、メッセージを送信した後に、予約やデリバリーに結びつけることも可能です。これにより、新メニューの紹介から、すぐに予約を促すこともできます。
LINE公式アカウントでは個人情報のやりとりができないため、必ずそれぞれの用途のシステムと連携する必要があります。
天候不良日の対策を行い、売上ロスを削減する
日本では、年間の約30%が雨やその他の天候不良日です。この中には台風や記録的な大雪など、集客0を避けられないことがある場合もあります。何もしなければ、雨の日に売上が下がる飲食店は、3日に1日の売上ロスを防ぐことができません。
雨の日の集客の対策で最も効果的なのは、予約制を採用することです。予約をすることで、キャンセルポリシーが設定されていると、雨が降っている程度のことでキャンセルされることがありません。そのため、平常時も可能な限り予約をすると、良い席を選べるなどの特典を付与することで、予約を増やすことを心がけましょう。
この他に、EBILABOが提供する来店予測AIを活用することで、天候によっての集客の見込みを予測することができます。これにより、集客に適した仕入れとシフトの組み立てを事前に行うことができます。
無断キャンセル対策(ノーショー)
無断キャンセルのことをノーショーと呼びます。
無断キャンセルは、全体の予約の約1%を占めていると言われ、売上への大きな影響を及ぼします。無断キャンセルが発生すると、予約した席が空席となり、その分の売上が損失となります。また、予約に基づいて仕入れた食材が余ってしまい、保存期間の短い食材は廃棄せざるを得ない場合もあります。これは、直接的な売上減少だけでなく、無駄なコストを生むため、事実上の損失となります。
無断キャンセルを防ぐための対策は各社で行われています。例えば、無断キャンセルの保険が提供されているサービスもありますし、予約台帳システムのTableCheckでは、クレジットカードを事前に登録させることで、無断キャンセルをした場合にキャンセルポリシーに準じた料金の請求を行うことができます。また、トレタでは、無断キャンセルが起こった時に、請求会社が取り立てを代行してくれるサービスがあります。
このような対策を通じて、無断キャンセルによる売上損失を最小限に抑え、安定した売上を確保することが可能となります。
最終更新日 : 2024年7月12日